企業が動画を利用してビジネスを行うことが増えてきている中、動画コンテンツの保護としてコピーや違法ダウンロードを防ぎたいという悩みをお持ちの方も多いでしょう。
動画のコピー防止や違法ダウンロード防止として代表的な対策が暗号化配信やDRMです。
今回は企業が動画のコンテンツ保護やコピー防止策で重要な暗号化配信とDRMの違いについてご紹介致します。
目次
動画配信のコピー防止策について
YouTubeや他のSNSのように動画を拡散して多くの人に見てもらいたい場合もあれば、ビジネス利用や有料で動画を販売したい際などに動画をコピーされたくない、意図しないダウンロードを防ぎたい、動画を勝手にSNSにアップロードされたくないといったニーズも多いはずです。
このようなお悩みをお持ちの方であれば、動画配信のコピー防止策について知っておくことが重要です。
動画配信のコピー防止策はいくつかの方法がありますが、最も多く利用されているのが暗号化配信とDRMでしょう。
聞いたことはあってもなんとなくしか意味を理解していない方や、違いについて詳しく知っている方は少ないと思いますので詳しく見ていきましょう。
ネット動画の暗号化配信について

ネット動画の暗号化配信とは動画コンテンツデータを暗号化し、再生時に暗号を解除しないと視聴できなくする方法や技術となります。
もし動画データをコピーしても、暗号を解く鍵がないと視聴することが出来ません。
iOSやAndroidで動画配信をする場合には、HTTP Live Streaming(HLS)方式の暗号化機能であるAdvanced Encryption Standard (AES)を利用して暗号化配信が行われています。
暗号化配信の技術自体は一般的にオープンとなっており、実装の手間はかかりますがライセンス料などは発生しません。
ネット動画のDRMについて
DRMとはDigital Rights Managementの頭文字の略称で、デジタル著作権管理やデジタル著作権保護という意味です。
音楽や映像、電子書籍コンテンツなどに対して違法コピーを制限したり、コピーされたデータを再生できないよう視聴制限をしてデジタルコンテンツの著作権保護の仕組みとして提供されている技術や方法の総称として使われています。
DRMを用いることで一定期間しか再生が出来ないように制限すること、コンテンツの違法なコピーやダウンロードを防ぐこと、コンテンツの再生回数に制限を設けることなどが可能です。
例えばAmazon prime video、Hulu、Netflixなど映画やドラマなどを扱っている動画サービスでは、DRM技術が使われています。
代表的な動画配信のDRMサービス
代表的な動画配信のDRMサービスを見ていきましょう。
PlayReady(プレイレディ)
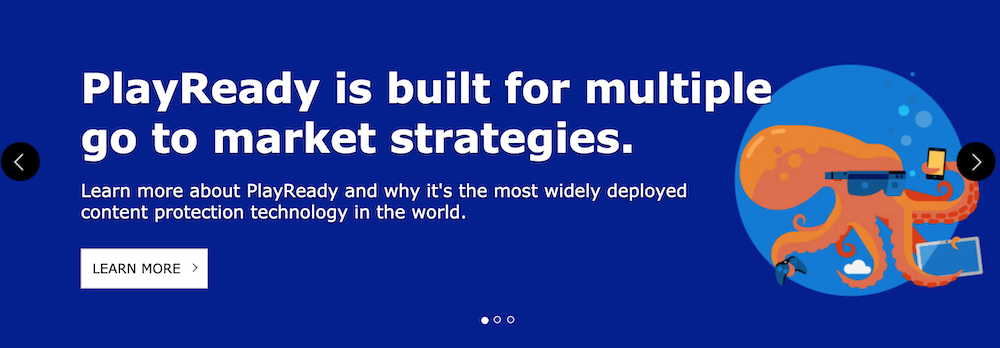
PlayReadyはマイクロソフト社が開発しているDRMです。DRMと言えばPlayReadyを想像される方も多いと思います。
Internet ExplorerやMicrosoft EdgeのブラウザではHTML5ベースの技術が利用されています。
Windows Media Video、Windows Media Audio、H.264など主要な形式のコンテンツファイルに対応しており、XboxやスマートTV、アプリでも使用されています。
Widevine(ワイドバイン)
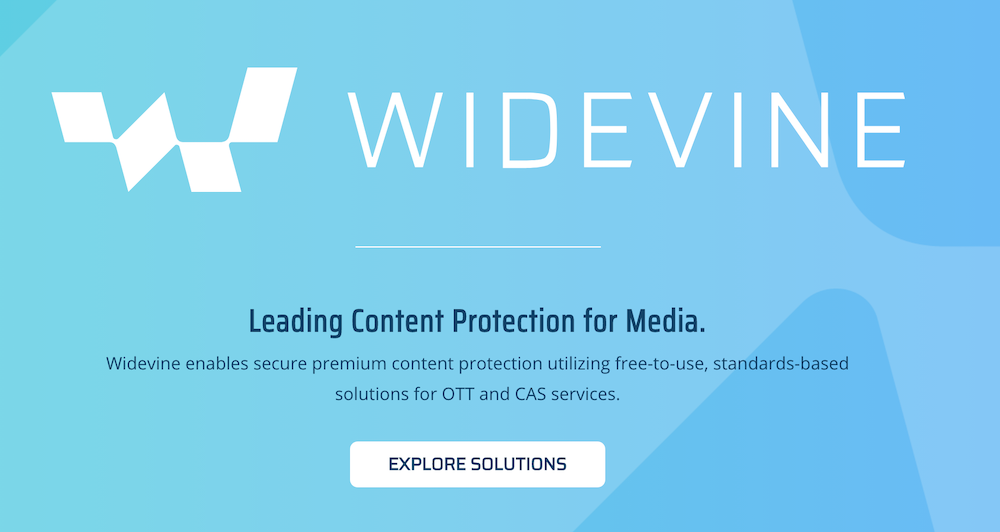
参考:Widevine
Widevineは、アルファベット(Googleなどの親会社)が買収したことによって傘下になったWidevine Technologies社が提供しているDRMです。
WidevineではGoogle ChromeやAndroid TV、アプリでのDRM配信に利用されていることが多いです。
Adobe Primetime DRM
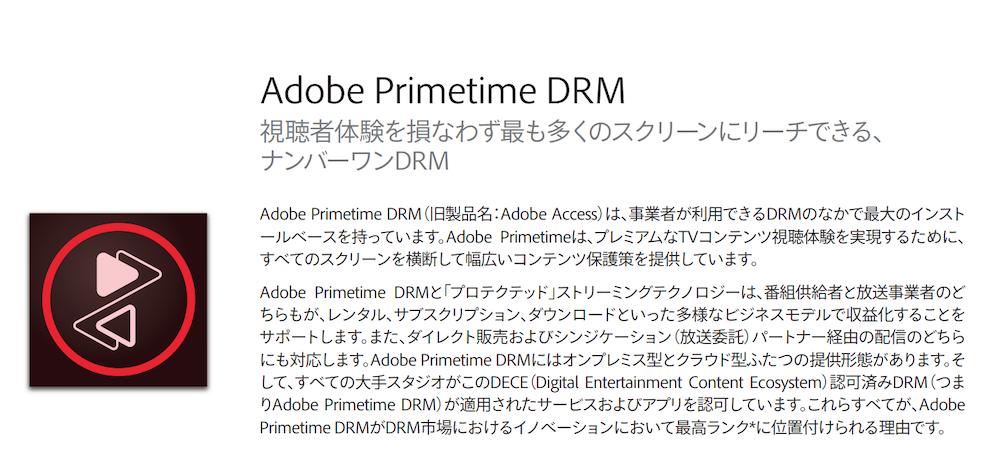
Adobe Primetime DRMはAdobe社が提供している動画配信サービスのAdobe PrimetimeにDRM機能を持たせたサービスです。
クラウド、オンプレミス両方に提供しており、HTML5ベースの技術を採用していることから世界中で多く利用されています。
FairPlay(フェアプレー)
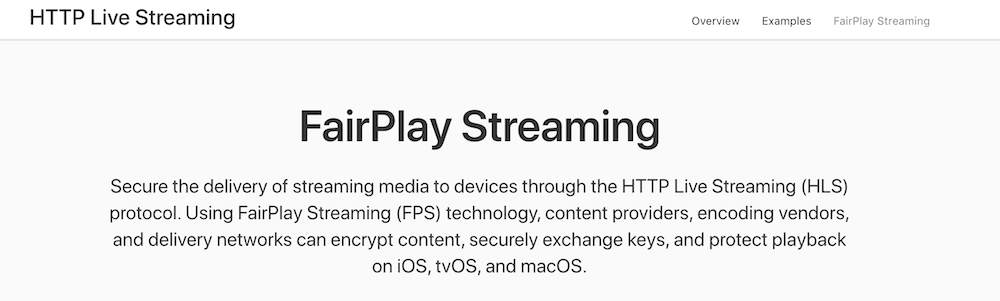
FairPlay(フェアプレー)はAppleのQuickTimeマルチメディア技術に内蔵されたDRMで、iPod、iTunes、iTunes Storeに使用されています。
iTunesと共にiTunes Storeから購入したそれぞれのファイルはFairPlayと同時にエンコードされています。
DRMを利用する方法と注意点
代表的なDRMサービスをご紹介致しましたが、DRMを利用するには比較的高い技術と金額がかかるため、自社で構築するのは難しく専門のベンダーにお願いすることが一般的です。
そのため、TV局や映画などの著作権が含まれているコンテンツや高い機密情報を含むコンテンツなど、セキュリティ対策が必要な場合には高い効果が期待できますが、実装に手間と費用がかかるため費用対効果をしっかりと考えてから利用することが重要です。
また、DRMを利用するとブラウザや端末に制限がかかることも多く、ユーザーの利便性も損なわれることも少なくありません。
自社で実装と運用を行うのが難しい場合には、動画配信プラットフォームにDRMがオプションとして組み込まれている場合もありますので、検討してみても良いでしょう。
暗号化配信とDRMの違いについて

上記で暗号化配信とDRMについてご紹介しましたが、違いについてまとめたいと思います。
コストの違い
暗号化配信にはライセンス料などは発生しませんが、DRMサービスは各社が独自技術を元に開発をしていることからライセンス料を支払うことが一般的です。
ここが一番の違いとなるでしょう。
技術の違い
DRMは各社が独自技術を元に開発をしていることから、利用に当たっては各社の技術を理解しなくてはなりません。
例えばWidevineを利用できるようにベンダーパートナーになるためには、Widevine主催のトレーニングへの参加が必須となります。
Widevineパートナーになるための要件として1社で2名以上の資格保有者が必要となり、英語での研修を受ける必要があるため日本の企業では数社程度しかいなかったはずです。
暗号化配信は技術的に利用できる会社や予め組み込まれている動画配信システムも多いため比較的簡単に利用できる技術になります。
視聴端末の違い
DRMのように高い技術を利用するとその分視聴者にとって不利益となる場合が多いです。
例えばブラウザの制限や視聴できない端末があることも多く、特定の環境下でしか視聴できないために高いコンテンツ保護を実現しています。
暗号化配信とDRMどちらを使うべきかの判断
海外ドラマやハリウッド映画のように非常に高いレベルでコンテンツ管理が必要なものであればDRMの利用を検討しても良いと思いますが、一般企業が利用するビジネス動画であればコストや手間を考えるとほとんどの場合は暗号化配信で十分だと言えるでしょう。
特別なコンテンツ以外ではDRMを使わない、DRMフリーという制限をかけないという流れが一般的になってきています。
多くのユーザーが好きなタイミングと端末で視聴ができる方がメリットとして大きいため、わざわざコストを払ってコンテンツに制限をかけることが事業にとってメリットにならないという判断をしている会社が増えてきました。
国内のテレビ局や動画配信サービスを提供している事業者でもDRM配信は行わずに暗号化配信で対応している場合が多いようです。
著作権保護について正しく理解し、費用対効果から方針を決めよう
デジタルコンテンツが一般的になってきた昨今では、提供者にとって著作権保護をどこまで行うのかが、ますます重要となってきています。
年々新しい技術が登場するものの、残念ながらこの仕組みを突破しようとする動きも盛んに行われており、一度導入したから必ず安心というわけではありません。
また、ネット上の動画を完全に保護することは難しいため、それを踏まえてコピー防止やコンテンツ保護にどれぐらいのコストをかけることができるかを会社の方針として決めておきましょう。
詳しい技術がわからなくても自社で動画や音声配信を行いたい場合には、動画配信システムを提供している会社やDRMに詳しいベンダーに一度相談してみることも良いでしょう。
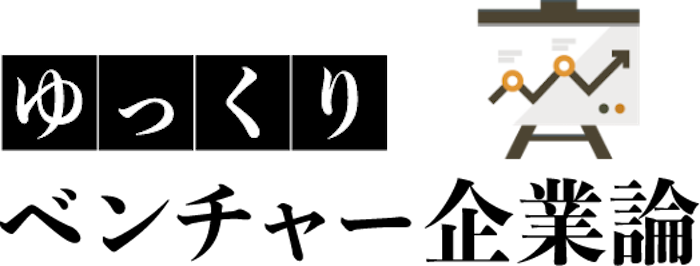
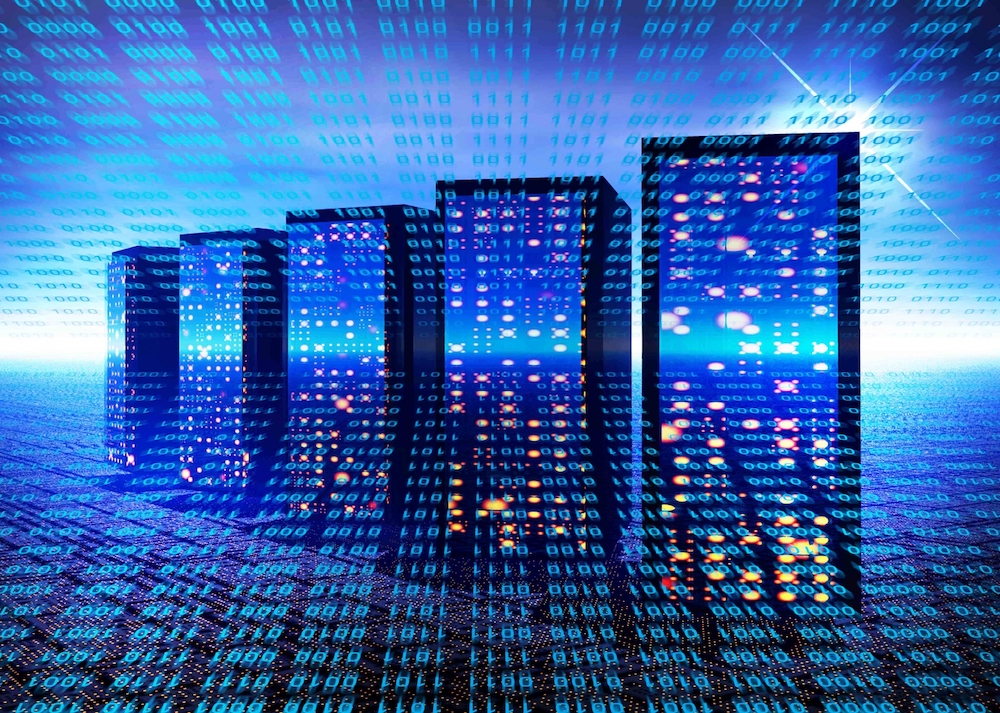



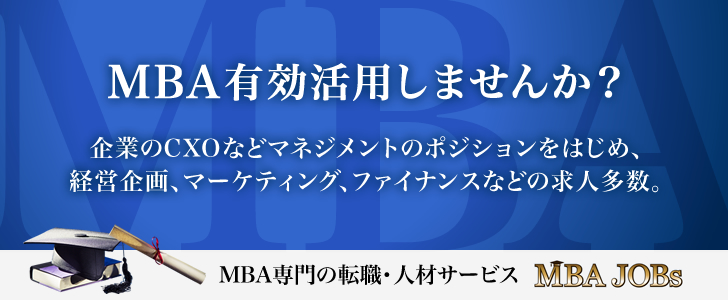




-の市場規模-市場動向-について-300x200.jpg)









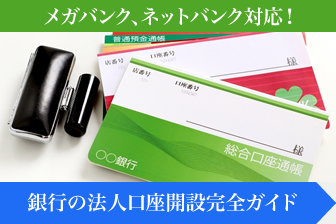













コメントを残す